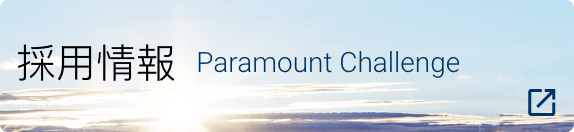専門家に聞く!ヘルスケア情報
丈夫な骨づくりを助けるビタミンD 適度な日光浴で慢性的不足を回避
2024年9月掲載

国立環境研究所
地球システム領域
特命研究員
中島 英彰(なかじま ひであき)先生
ビタミンDは「骨のビタミン」とも呼ばれ、カルシウムの吸収を促し骨を丈夫にします。これまで日本人ではビタミンD不足はあまり心配されていなかったのですが、2000年以降、特に若い女性を中心にビタミンD不足が指摘されるようになりました。その最大の原因は美白ブームなどによる過剰な紫外線対策だとされます。ビタミンD不足にならないためには紫外線とどう付き合えばよいのか、国立環境研究所特命研究員の中島英彰先生にお聞きしました。
ビタミンDは紫外線により皮膚でも生成
「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、18歳以上の成人の1日の摂取量目安は男女ともに8.5マイクロ(マイクロは100万分の1)グラムとなっています。一方、「令和元年国民健康・栄養調査」によると日本人のビタミンDの平均摂取量は6.9マイクログラムです。この数字からは、日本人は慢性的にビタミンD不足になっているように見えますが、それでも日本人はビタミンDが不足することは少ないとされています。
中島先生は「それは、ビタミンDは食品から摂取する以外に、日光の紫外線を浴びることによって人が体内にもっているコレステロールの一種から皮膚の中でも生成されているからです。日照に恵まれた日本では、仕事や買い物に出掛けたり、日中普通に活動していれば、皮膚で生成されるビタミンDが十分貯まっていくので、ビタミンD欠乏は起こりにくいとされてきました」と説明します。
「ところが2000年頃から日本人の特に若い女性でビタミンDが不足して、骨の疾患が増加しているという報告が増えてきました」と中島先生は続けます。「1985年に南極のオゾンホールが発見されて以降、紫外線の皮膚や目への有害な作用を警戒する情報が世の中に広まったことから、特に若い女性では、美白ブームなどもあいまって、日光が皮膚に当たるのを極度に避ける傾向が強まりました。実際には、季節にもよりますが短い時間でも日光浴をすればビタミンDをある程度生成することは可能です。しかし、昨今の紫外線を避ける対策はどんどん“完璧”になっていて、ビタミンDの生成もできなくなっているのです」と注意を促します。
以前、大阪樟蔭女子大学の津川先生たちの研究グループが東京の12歳〜18歳の中学・高校生1,360人の血液を調べたところ、ビタミンDの栄養状態は、男子は30.2%、女子は47.7%が欠乏という結果でした。ビタミンDが欠乏すると、骨が軟化したり変形します。成人では骨軟化症、子どもではくる病などの骨の病気が起きます。高齢者では骨の密度がスカスカになって骨折しやすくなる骨粗鬆症になります。「赤ちゃんの場合は妊娠中は母体から、出生後は母乳からビタミンDが供給されます。そのためお母さんがビタミンD不足だと、子どももビタミンD不足になってしまいます。最近の若い女性のビタミンD不足は、本人の骨密度が低くなるだけでなく、赤ちゃんのビタミンD不足にも影響を及ぼすので、問題視されています」と中島先生は指摘します。
安全にビタミンDができる時間を算出
「紫外線は確かに過剰に浴びると皮膚に紅斑や日焼けを起こし、しみ・シワのもとになります。国立環境研究所では全国の研究機関と連携して11カ所の観測拠点で降り注いでくる紫外線量を継続的に測定してきました。これらの観測データから、それぞれの地点における皮膚にトラブルを起こす時間を割り出しました。併せて、ビタミンDの生成に必要な時間を算出しました。それぞれの季節における目安の例を表に示します。表中の「紅斑(MED)」は、皮膚に有害となる紅斑紫外線量=MED(最少紅斑紫外線量)にいたる日光照射時間です。これ以内であれば安全にビタミンDができます」(中島先生)。

中島先生は「日本列島は南北に長いので、北海道と九州ではずいぶん時間が違います。いずれにしても、皮膚にトラブルが起こらない程度の時間でもビタミンDは十分生成されていることが分かります。また、冬季は北日本方面では紫外線による皮膚への悪影響を心配する必要はないことも分かると思います。逆に、北海道などでは日光浴だけでは十分にビタミンDを補えなくなります。冬季は本州の日本海側や降雪地帯も同様に日照量が少なくなって十分に補えなくなります」と言います。
なお、北海道から沖縄まで各観測拠点の毎日のビタミンD生成量と紫外線量は以下のWebサイトで公開されていて、リアルタイムに見ることができます。
◆国立環境研究所地球環境研究センター「ビタミンD生成・紅斑紫外線量情報」
食品で補うにはサケ、イワシがお勧め
ビタミンDの不足や欠乏は一般的な血液検査の検査項目にはなっておらず、自分で知ることはできないので、不足になりやすい生活をしている人は、日頃から意識してビタミンDを含む食品の摂取を心がけることが必要です。
中島先生は「食品で補うには魚がお勧めです。シイタケやキクラゲなど、きのこ類もビタミンDが比較的多く含まれていますが、十分量を取るにはかなり多量の摂取が必要になります。魚ならば、イワシ1尾、あるいはサケ1切れは1日の必要摂取量の目安になります。残念ながら肉類にはビタミンDはあまり含まれていません。欧州やカナダではビタミンDの不足を補うビタミンD強化食品やサプリメントも多数利用されていますが、日本ではサプリメントの利用はあまり一般的でない上に、過剰摂取による逆効果もあり得ます。日照によって皮膚で生成されるビタミンDの場合は、体内に必要量がたまるとそれ以上生成反応は進まない仕組みなので、過剰摂取になる心配はありません」と解説します。
最新の研究によれば、ビタミンDは免疫力を高めてがんや心筋梗塞などの発症リスクを低減したり、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症の予防にも効果があることが分かってきました。中島先生は「昨今、紫外線は悪者扱いされている印象がありますが、身体の健康に重要なビタミンDを作ってくれるという大事な役割を担っています。ぜひ観測データも参考にして、上手に付き合ってください」と話しています。