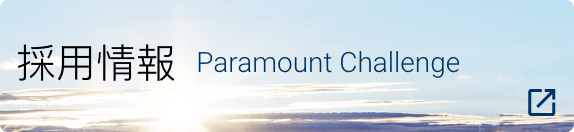専門家に聞く!ヘルスケア情報
骨粗鬆症が原因の二次骨折に注意 骨折を機に骨粗鬆症治療を開始し、継続することが重要
情報誌けあ・ふるVOL.118(2024/1)掲載

名古屋大学医学部
整形外科
講師
竹上 靖彦 先生
加齢とともに骨が弱く、もろくなる骨粗鬆症。進行すると少しの外力が加わっただけでも折れてしまう、脆弱性骨折を起こしやすくなります。大腿骨の脆弱性骨折を起こした後、反対側の大腿骨やそのほかの部位が再び骨折することを「二次骨折」と言います。大腿骨骨折をした患者が反対側も骨折すると1年後の死亡率が格段に上がることもわかっています。二次骨折を予防するにはどうしたらよいのかについて、名古屋大学医学部講師の竹上靖彦先生にお聞きしました。
骨粗鬆症で起こる脆弱性骨折
高齢化に伴い、骨粗鬆症の患者が年々増加しています。骨粗鬆症とは、骨の量(骨量)が減って骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気です。特に閉経後の女性に多くみられ、現在の日本国内の患者数は約1300万人と推計されています。
骨粗鬆症の患者では骨が弱くもろくなるため、少しの外力が加わっただけでも折れてしまう脆弱性骨折を起こしやすくなります。頻度が高いのが背骨の骨折(脊椎椎体骨折)、脚のつけ根の骨折(大腿骨近位部骨折)、手首の骨折(橈骨遠位端骨折)、肩のつけ根の骨折(上腕骨近位部骨折)などです。
中でも大腿骨近位部骨折は、日常生活の動作が大きく障害され、生活の質も下がる代表的な骨折です。骨盤に結合している大腿骨は、くびれて細くなった部分が頸部、その下の太くなっている部分が転子部で、大腿骨頸部骨折、大腿骨転子部骨折を併せて大腿骨近位部骨折と呼んでいます(図1、図2参照)。

大腿骨近位部骨折をきっかけに
竹上先生は「大腿骨の付け根は人間の関節の中で最も奥にあり、通常ちょっとやそっとの転倒などで折れるものではありません。そこが折れるということは、骨粗鬆症が進行していることの現れと言えます」と話します。
骨粗鬆症そのものは痛みはほとんどなく、自覚症状がないため治療も積極的に行われていないのが実情です。「名古屋大学のデータでは、大腿骨近位部を骨折した患者さんの7%しか、骨粗鬆症の治療は行われていませんでした。また他の研究データでは、大腿骨近位部を骨折した患者さんの1年後の骨粗鬆症治療率はわずか%でした。ですから、一方の大腿骨の骨折をきっかけとして、もう片方の骨折や他の部位の脆弱性骨折を予防するため、骨粗鬆症治療を積極的に行おうという動きが高まっています。それが二次骨折予防です」と竹上先生は話します。
生命予後にも大きく影響
ところで、高齢者の大腿骨近位部骨折は、受傷すると日常生活が困難となり要介護状態に移行するケースも少なくありません。その結果、生命予後にも大きく影響することが国内外の研究で明らかになっています(表1、表2)。
竹上先生は、「大腿骨近位部骨折を起こした患者の1年後死亡率は13〜18%と、健常な人よりも高くなります。術前の歩行能力を回復するのは50%で、術前に日常生活で自立していた人の20〜60%が介護を要するようになり、10〜20%が自宅から介護施設に移っています。さらに、大腿骨近位部骨折を起こした人の反対側の骨折の危険度は2・2倍に上昇、反対側も骨折した人の1年後の死亡率は%と格段に高まります」と話します(表1、表2)。

骨折リエゾンサービスの試み
二次骨折予防の重要性の高まりとともに、全国の先進的な医療機関で取り組みが始まっているのが、骨折リエゾンサービス(FLS:Fracture Lieson Service)です。
「大腿骨に限らず、骨折の治療はともすれば骨がつながったり、人工骨頭を入れたりすれば終了と考えられてきました。しかし、それでは患者さんの二次骨折を防ぐことはできません。そこで全国の先進的な医療機関で始まっているのが、骨折リエゾンサービスです。医師、看護師、リハビリスタッフ、薬剤師など様々な職種の連携により、脆弱性骨折患者に対する骨粗鬆症治療開始率、治療継続率を上げるとともに、転倒予防を実践することで二次骨折を防ごうという試みです」と竹上先生。ちなみにリエゾンはフランス語で「連携・橋渡し」という意味です。
病院とかりつけ医が連携
FLSは日本骨粗鬆症学会、日本脆弱性骨折ネットワークによって作成された「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」が基本になっています。
表3に示すように、対象患者の特定、二次骨折リスクの評価、投薬を含む治療の開始、患者のフォローアップが大きな流れとなります。対象は50歳以上のすべての種類の脆弱性骨折患者とされており、大腿骨近位部骨折と脊椎椎体骨折の患者が最優先されるとしています。
竹上先生らも、名古屋市を中心に愛知県内の複数の医療機関とで、骨折リエゾンサービスのネットワーク作りに取り組んでいます。「骨粗鬆症の治療は、手術を行う急性期の病院、リハビリを行う回復期の病院、そして退院した後に担当するかかりつけ医が連携して、継続的に行っていくことが大切です。そうした連携や退院後の患者さんの定期的なフォローに役立つよう、患者向けの『骨折予防手帳』を作って希望する医療機関に配布しています」(竹上先生)。

治療薬は10年ほどで大きく進歩
では、大腿骨近位部骨折など、脆弱性骨折を起こした患者やその家族は、二次骨折予防のためにどうしたらよいでしょうか。
竹上先生は、「高齢の方で、骨折の治療は終わったが骨粗鬆症の治療は特にしていないという人は、医療機関に相談して、骨粗鬆症治療の必要性についてまず相談してみることが大切です。また、近隣でFLSに取り組んでいる医療機関などを検索して見つかれば、そこを受診するのも一法でしょう」と話します。
骨粗鬆症の治療は薬物療法が中心で、食事療法、運動などを並行して行っていくことになります。治療薬はこの10年ほどで進歩しており多種多様です。大きくは、骨吸収を抑える薬(ビスホスホネート、抗RANKL抗体など)、骨形成を促進する薬(副甲状腺ホルモンなど)、骨吸収を抑えて骨形成を促進する薬(抗スクレロスチン抗体など)、骨に必要な材料を補充または骨代謝をサポートする薬(活性型ビタミンD3など)の4種類に分けられます。「注射か服薬かの違いもありますし、投与間隔も毎日から6カ月に1回まで様々です。薬の価格も違います。症状や副作用の状況、経済状態などを考えながら処方を決めていく必要があり、治療に当たっては専門医だけでなく薬剤師などのサポートも不可欠です」(竹上先生)。
65歳以上になったら骨密度を測定
二次骨折予防は、骨粗鬆症が既に進んでしまった人を一度目の大腿骨近位部骨折で拾い上げ骨粗鬆症の治療を開始しようというものです。竹上先生は、「本来ならば、最初の骨折も避けたいところです。そのためには、特に女性は歳以上になったら、専門の医療機関で骨密度を定期的に測定し、自分が骨粗鬆症かどうかを確認するようにしてください。そして、治療を受ける場合は、大腿骨や背骨の骨密度が正確に測れるDEXA法の骨密度測定装置がある施設がお勧めです。そして、治療を開始したら、それを継続することが大切です」と話しています。