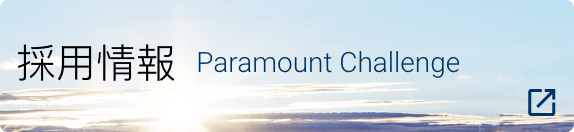専門家に聞く!ヘルスケア情報
難聴は認知症の危険因子、その最新対処法 中等度難聴では補聴器の使用も検討を
情報誌けあ・ふるVOL.110(2022/1)掲載

オトクリニック東京 院長
小川 郁 先生
加齢などによって聴力が落ちることで発症する難聴。2017年、国際アルツハイマー病協会国際会議において、難聴は高血圧、肥満、糖尿病などと共に認知症の危険因子の一つに挙げられました。さらに2020年の同会議では、「予防可能な12のリスク因子の中で、難聴は認知症の最も大きなリスク因子である」との指摘もされています。難聴の原因や認知症との関係、補聴器の使用方法のポイントなどについて、慶應義塾大学名誉教授で、オトクリニック東京院長の小川郁先生にうかがいました。
加齢で起こる難聴は感音難聴
難聴とは耳や神経、脳の異常で音が聞こえにくい状態の総称です。大きく分けると、「伝音難聴」、「感音難聴」、そして伝音難聴と感音難聴が混在した「混合性難聴」の3つに分類されます。 伝音難聴は、音がうまく伝わらないために聞こえにくくなるというもので、主に外耳、中耳の病気によって起こります(図1参照)。例えば、耳垢が溜まっていたり、中耳炎による炎症などで鼓膜が正常に振動せず音がうまく伝わらないのも伝音難聴です。耳が塞がったような感じがするのが特徴です。
これに対し感音難聴は、内耳から、最終的に音を感じ取る聴神経(蝸牛神経)などの部分に何らかの障害が生じることで起こります(図1参照)。音が小さく聞こえるだけでなく、騒がしい環境などで話の内容が理解しづらくなったりします。患者数が最も多いのが感音難聴で、高齢になると発症する加齢性難聴もこの感音難聴です。「内耳の働きは、外耳、中耳から入ってきた音、つまり物理的振動を神経の電気信号に変換するというものです。その働きをするのが内耳にある有毛細胞です。とても小さな毛でできており、ピアノの鍵盤のように並んでいます。この一つひとつの有毛細胞が音で振動することで電気信号を作り出しているのです。加齢によってこの有毛細胞がダメージを受け、数が減ったり機能しなくなると、音が聞こえづらくなります。寿命がどんどん伸びて、高齢者も健康になっていますが、その分、有毛細胞が働く期間も長くなっています。有毛細胞を増やしたり、機能を強めたりはできないので、高齢化によって難聴の方が増えていくのは自然の流れとも言えます」(小川先生)。
加齢性難聴は 30 代から始まる
加齢性難聴は30代から始まる加齢性難聴は高齢になってから始まると考えがちですが、「30代から既に始まっている」と小川先生は話します。 「人間の耳は元々、20ヘルツ(低音)から2万ヘルツ(高音)まで非常に幅広い音を聞く能力があります。30代くらいから1万6000〜2万ヘルツといった高い周波数の音は聞こえなくなってきます。こうした高い周波数の音は生活とは直接関係なく、自覚することはありませんが、聞き取ることができる周波数の上限は、加齢によってどんどん下がっていきます。上限が4000ヘルツくらいになると、言葉の聞き取りに支障が生じ始めます。それがだいたい60歳前後です」と小川先生。
ちなみに、日本語は約500から2000ヘルツくらいまでを使う言語で、4000ヘルツ近くまで使う英語やフランス語などよりも聞き取りやすいそうです。「日本語の母音は500 〜1000ヘルツで、子音は2000ヘルツ前後です。ですから、加齢による難聴の場合、『さしすせそ』『かきくけこ』などの子音の聞き取りが悪くなることから始まります。『さとう』『かとう』の聞き間違えなどはその典型です」(小川先生)。
難聴の程度はどれだけ小さな音まで聞こえるかで分類されます。音の大きさは聴力レベル(dB:デシベル)で表現されます。聴力検査で測った聴力レベルが25デシベル未満なら正常、25デシベル以上になると難聴に分類されます(表参照)。40デシベルまでの軽度難聴の場合には、補聴器をつけなくても一般的な会話は聞き取り可能です。
難聴は認知症のリスクを高める
難聴は認知症のリスクを高める大きな因子であることが最近の研究でわかってきています。
2017年、医学雑誌『ランセット(Lancet)』の認知症の専門家からなる国際委員会が、国際アルツハイマー病協会国際会議において、認知症は「教育不足」「難聴」「高血圧」「肥満」「喫煙」「うつ」「社会的孤立」「運動不足」「糖尿病」の9つのリスクを改善することで、発症を遅らせたり、発症を約35%予防する効果が期待できると報告しました。同委員会はさらに2020年、その後の研究結果も踏まえ、この9リスクに「過剰飲酒」「頭部外傷」「大気汚染」の3つを加えた12のリスクが認知症の発症に寄与していると報告しました(4ページ図2参照)。
「この時の報告では、発症を予防できるのは約40%の認知症で、うち中年期(45〜65歳)の難聴を改善することで、認知症の8%を減らすことができるとしています。8%という数字は他のリスクよりも大きく、難聴が最大のリスク因子ということになります」(小川先生)。
なぜ難聴が認知症のリスクになるのかについて小川先生は、「いくつかの仮説があります。一番わかりやすいのはカスケード仮説と呼ばれるものです。聞こえないと、うまくコミュニケーションができない。コミュニケーションができないと、楽しいとか、悲しいとかいう情動反応が起きにくくなる。また、会話がうまくできないので出歩かなくなる。そうすると、社会的にだんだん孤立し、認知機能も落ちていく。こういう悪循環が認知機能を低下させるという説です。この他、認知症と難聴に共通する発症危険因子として尿病や高血圧の原因となる微小循環障害があり、それが関係しているという説もあります。一つだけの原因ではなく、複数の原因によって、難聴と認知症が関連していると考えられます」と説明します。
症状を改善する薬剤はない
人口の高齢化によって増加傾向にある加齢性難聴ですが、それを治したり、症状を改善する薬剤はまだ登場していません。
「新薬の開発は進んではいますが、実用段階の薬はまだありません。ですから、難聴にならないようにするため、若い時からの予防が重要です。長期間の耳の酷使、例えば大きな音で音楽を長年聞き続けるといった生活習慣を改めれば、難聴の進行はある程度は抑えられると考えられます。加えて、生活習慣病に対する早めの対応も重要です。内耳は微小な血管から栄養を得ていますので、生活習慣病によって血液が粘稠になると、それだけ血流が悪くなり、内耳にもよくありません」(小川先生)。
補聴器はトレーニングが必要
加齢性難聴の決定的な治療法はまだありませんが、聞こえにくさを改善する方法はあります。補聴器の使用です。補聴器は、音を拾い増幅して聴神経がある内耳に送る機器です。耳に掛けるタイプ、耳の穴に入れるタイプなどがあります。
「聴力レベルが40デシベル以上の中等度難聴で、聞こえ方を改善させたい方には補聴器の使用を勧めます。70デシベル以上の高度難聴の方には、人工内耳を埋め込む手術があります。加齢性難聴の場合、進んでも中等度までなので、補聴器使用が一般的です。その場合、両耳に装着するのが基本です」と小川先生。
小川先生は「補聴器は眼鏡のように使ってすぐ効果が実感できるものではありません」と話します。「補聴器を付ければはっきり聞こえるようになると期待される人は多いですが、そんなに簡単ではありません。そもそも、音を感じ取る有毛細胞が減ってしまっているので、単純に音を大きくするだけでは快適には聞こえないのです。すぐに矯正できる眼鏡と違い、補聴器を通して入ってきた音から言葉を聞き取るトレーニングをし、補聴器の音を脳が理解できるようにならなければなりません。購入前に、耳鼻咽喉科医の指導の下、3カ月ほどトレーニングを行うのが理想です」。
また、補聴器は一度購入すれば終わりではなく、定期的な聴力検査や機器の調整も必要です。補聴器の相談には、日本耳鼻咽喉科学会のホームページに掲載されている補聴器相談医の名簿が参考になります。補聴器相談医に補聴器適合に関する診療情報提供書を書いてもらい、認定補聴器専門店等で購入するという流れが基本です。 「補聴器を町中の販売店で買って、装着してみたがすぐにやめてしまったという人は少なくありません。必ず補聴器相談医による診察・検査を受け、補聴器の専門店などで購入するようにして下さい」と小川先生は話しています。